目次
小見出しも全て表示
閉じる

王道の味。定番の和菓子レシピ6選
1. ふっくらしっとり。蒸しまんじゅう
蒸し器で作る基本の蒸しまんじゅうレシピです。薄力粉とベーキングパウダーのふっくらとした生地と、しっとりあま〜いこしあんの相性は抜群。寛ぎのひとときに、やさしい味わいの蒸しまんじゅうでほっこり癒やされませんか?
2. 切り餅を使えば簡単♪ 黒豆大福
黒豆をゴロッと入れて、食べ応え抜群な大福を作りましょう。もち米やもち粉がなくても切り餅を使えば簡単。餅に塩を加えて塩大福にしたり、中身をつぶあんにしたり、自分好みにアレンジをするのもおすすめです。
3. ひんやりスイーツ。水まんじゅう
ひんやり冷たい和菓子といえば、水まんじゅう。中のこしあんが透き通って見える涼しげな見た目とつるんとした喉越しで、清涼感を感じられるひと品です。葛粉やわらび粉を使うのが一般的ですが、片栗粉で作ることもできます。
4. 香ばしさ×やさしい甘味。きんつば
つぶあんは粉寒天で固めてしっとりと、衣は薄力粉と白玉粉を使ってもちもちとした食感に仕上げます。香ばしい薄皮と、やさしい甘さのつぶあんのコンビネーションがたまりません。ほろ苦い緑茶や抹茶によく合いますよ。
5. しっとりふわふわ。本格どら焼き
人気の焼き物和菓子、どら焼き。生地をふわふわにするために、薄力粉にベーキングパウダーを加えます。きび砂糖とはちみつ、みりんでやさしいコクのある甘さに仕上げましょう。つぶあん入りで、ずっしり食べ応えのあるひと品です。
6. アレンジいろいろ♪ 薄皮たい焼き
おやつとしてよく食べられているたい焼きは、親しみのある和菓子のひとつです。薄力粉に片栗粉と重曹を加えて、パリパリの薄皮たい焼きに仕上げます。もちもち派の人は、白玉粉と米粉を使うレシピがおすすめです。
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
レビュー(0件)




 -
-
レビューはまだありません
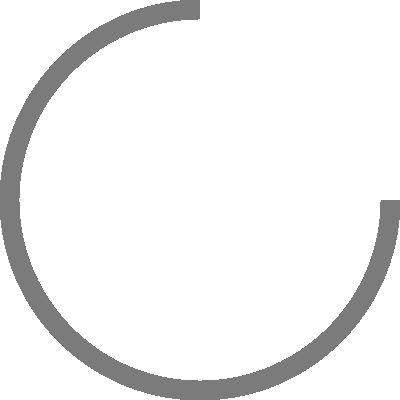

ユーザー名(ニックネーム)
評価(必須)


5.0
大満足のおいしさ。
定番料理にしたい。
画像(任意)
コメント(必須)

レビューが投稿されました
閉じる

このコメントを削除してもよろしいですか?
「」

コメントが削除されました
閉じる
和菓子の人気ランキング



































