目次
小見出しも全て表示
閉じる

茶巾寿司はハレの日にぴったりのお寿司!
具材入りの酢飯を薄焼き卵で包む茶巾寿司は、華やかな見た目でハレの日にぴったり。食卓に並べるだけで上品な雰囲気が演出できます。
やさしい味わいの薄焼き卵と、しっとりやわらかい酢飯の組み合わせが、ほっとする味わいでいやされます。「何が入っているのか想像するわくわく感も楽しい」と家族にも好評でした。酢飯に混ぜる具材に決まりはないため、手軽にアレンジが楽しめるのも魅力です。
やさしい味わいの薄焼き卵と、しっとりやわらかい酢飯の組み合わせが、ほっとする味わいでいやされます。「何が入っているのか想像するわくわく感も楽しい」と家族にも好評でした。酢飯に混ぜる具材に決まりはないため、手軽にアレンジが楽しめるのも魅力です。
上品でかわいらしい♪ 茶巾寿司のレシピ
調理時間
25分
簡単に作れる茶巾寿司のレシピです。漬物を混ぜるだけの五目寿司と、しっとり破れにくい薄焼き卵で作ります。高菜や柴漬けなど、お好みの漬物をご用意ください。数種類の漬物を混ぜたり、白いりごまを加えたりしてもおいしいですよ。薄焼き卵を焼くフライパンは、直径21~26cmのものが作業しやすくておすすめです。
材料(5~6個分)
茶巾寿司のコツ・ポイント
コツ・ポイント
- 卵液に片栗粉を加えて破れにくくする
- 五目寿司をあらかじめ握っておく
- お好みの漬物を使う
卵液に水溶き片栗粉を加えることで、破れにくく包みやすい薄焼き卵が作れます。なめらかで見た目のきれいな薄焼き卵を作りたい場合は、茶こしでこしてから焼きましょう。
五目寿司はあらかじめ茶巾型に握っておくことで、スムーズに包む作業ができますよ。五目寿司に入れる漬物はお好みのものをご用意ください。大きいサイズの漬物はみじん切りにし、漬物の塩気や甘みによって、合わせ酢の配合や漬物の量を調整するのがポイント。
五目寿司はあらかじめ茶巾型に握っておくことで、スムーズに包む作業ができますよ。五目寿司に入れる漬物はお好みのものをご用意ください。大きいサイズの漬物はみじん切りにし、漬物の塩気や甘みによって、合わせ酢の配合や漬物の量を調整するのがポイント。
下ごしらえ
三つ葉をさっとゆでる

Photo by Uli
鍋で湯を沸かして三つ葉を入れ、20~30秒ゆでてザルにあげます。
作り方
1.卵、水溶き片栗粉、塩を混ぜる

Photo by Uli
卵を割ってコシを切るように混ぜ、水溶き片栗粉と塩を加えて混ぜます。きれいな薄焼き卵を作りたい場合は茶こしでこします(省略可)。
2.フライパンで薄焼き卵を焼く

Photo by Uli
中火でフライパンを温め、薄くサラダ油をひいてなじませます。フライパンが温まったら弱火にして、卵液の1/6~1/5量を流し入れ、フライパンを傾けて全体に薄く広げます。
※フッ素加工されているフライパンを使います。直径26cmのフライパンで5枚、直径21cmのフライパンで6枚が目安です。

Photo by Uli
表面が乾いてきたら箸かヘラで持ち上げて裏返し、10秒ほど焼いて取り出します。これを繰り返して5~6枚の薄焼き卵を作ります。
3.合わせ酢の材料を混ぜる

Photo by Uli
米酢、砂糖、塩を混ぜます。砂糖の量は使用する漬け物の甘さによって調整します。
4.ごはん、合わせ酢、漬物を混ぜる

Photo by Uli
ごはんに合わせ酢をふりかけ、ヘラやしゃもじでさっくり混ぜます。ごはん全体がほぐれたら、漬け物を加えて混ぜます。
5.五目寿司をラップで握る

Photo by Uli
ごはんを5~6等分にし、ラップで茶巾型に握ります。
6.薄焼き卵で五目寿司を包む

Photo by Uli
五目寿司を薄焼き卵で包みます。なるべく等間隔になるようにひだを寄せて形をととのえます。
7.三つ葉で結ぶ

Photo by Uli
三つ葉を2~3本束ね、茶巾の上部でしっかり結んで完成です。
- 1
- 2
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
レビュー(0件)




 -
-
レビューはまだありません
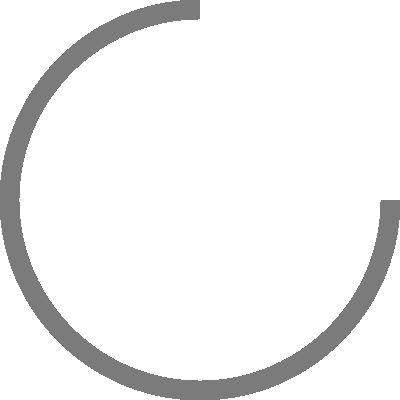

ユーザー名(ニックネーム)
評価(必須)


5.0
大満足のおいしさ。
定番料理にしたい。
画像(任意)
コメント(必須)

レビューが投稿されました
閉じる

このコメントを削除してもよろしいですか?
「」

コメントが削除されました
閉じる
米の人気ランキング

































