目次
小見出しも全て表示
閉じる

パクッと食べたい!お稲荷さんの作り方を伝授
運動会やお正月など、ハレの日に食べるイメージが強いお稲荷さん。実は、けっこうアレンジを加えることができる料理なんです!自分好みの具材を選び、お気に入りの組み合わせを発見すれば、オリジナルなお稲荷さんが作れますよ。
今回は、お稲荷さんの基本的な作り方をご紹介。さらに、おすすめの具材もチェックしていきます。油揚げを開いたり、ご飯を詰めるときにすこし手間取ることがあるかもしれませんが、大丈夫!何度もやっていれば上手になりますよ。
「お稲荷さん」の由来と歴史は?
お稲荷さんの語源は、キツネの神様である「稲荷神」から。稲荷神の使いであるキツネの好物はネズミの油揚げとされていました。いつからか豆腐の油揚げが神様に供えられるようになり、今度はそちらがキツネの好物とされるように。
豆腐の油揚げはキツネ、すなわち稲荷神の好物。その油揚げを使うお寿司なので「稲荷寿司」と呼ばれるようになったそうです。
お稲荷さんの基本レシピ
こちらでは基本的なお稲荷さんの作り方をご紹介します。油揚げを開くときや、ご飯を詰める際にすこしコツがいりますが、何度もやっていれば上手になるはず!
お稲荷さんの中に入れる具は、自分好みのものでOKですよ。いろいろな材料をためして、お気に入りの組み合わせを見つけてみてください。
材料(4人分)
作るときのコツ
- 煮汁で油揚げを煮る際は、底の深いフライパンを使うと、煮汁が全体に回りやすいのでおすすめ。鍋を使う場合は7分煮てから上下を返しさらに7分煮て、しっかりと1枚1枚に味がしみ込むようにしましょう。
- 煮汁の味はあまり濃くしてしまうと、お稲荷さん自体がしょっぱくなってしまうので、ほどほどに加減しましょう。包むときはあまりお米をギュウギュウと圧縮しないのがコツです。
作り方
1.油揚げの下準備をする

Photo by tumu
まな板に油揚げをのせて、上からお箸でコロコロと押さえつけます。

Photo by tumu
半分に切ってなかを開き、袋状にします。

Photo by tumu
お鍋でお湯を沸かし、油揚げを入れて1分ほど茹で、油抜きをしましょう。そのあとザルに上げて水を切ります。
2.油揚げを煮る

Photo by tumu
鍋やフライパンに煮汁の調味料を入れて火にかけ、砂糖が溶けたら油揚げを加えましょう。落とし蓋をして中火で煮て、煮汁がすこし残るくらいまで水分を飛ばします。そのあと、そのまま冷ましましょう。
3.酢飯を作る

Photo by tumu
ご飯を固めに炊き、ボウルに移したら合わせ酢を回しかけ、しゃもじで切るようにして混ぜます。うちわなどであおいで冷ましましょう。

Photo by tumu
すし飯を50gほどとって軽く握り、形を整えます。
4.油揚げに酢飯を入れて仕上げる

Photo by tumu
油揚げを両手で挟むようにして、軽く水気を絞り、すし飯を詰めます。そのあと形を整えて完成!口を閉じる場合は、両端をなかに折り、残った両端もなかに折り込みます。
お稲荷さんにおすすめの具
お稲荷さんの具は、いろいろな組み合わせを楽しめるのが大きな利点!おにぎりと一緒で、工夫次第で新しい「オリジナルな」お稲荷さんを作れます。
定番はにんじんや蓮根、しいたけなどを甘辛く煮てご飯に混ぜる五目稲荷。また、カリカリ梅と大葉、いりゴマを混ぜたものもさっぱりしておいしいですよ。
大人な味わいを堪能したい場合は、ワサビ味のものがおすすめ!ほうれん草とワサビを溶かしためんつゆをご飯に混ぜ、それを包みます。
- 1
- 2
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
レビュー(0件)




 -
-
レビューはまだありません
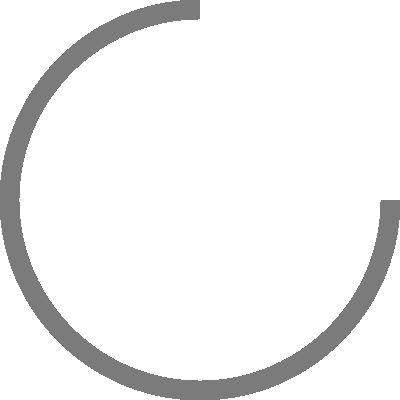

ユーザー名(ニックネーム)
評価(必須)


5.0
大満足のおいしさ。
定番料理にしたい。
画像(任意)
コメント(必須)

レビューが投稿されました
閉じる

このコメントを削除してもよろしいですか?
「」

コメントが削除されました
閉じる
いなり寿司の人気ランキング

































